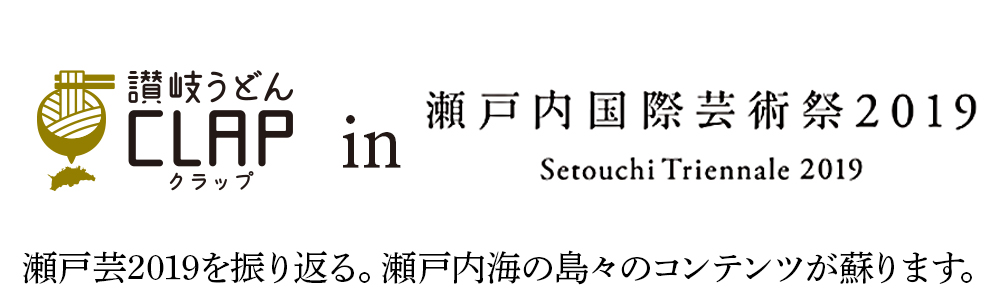「美味しい讃岐うどん」の正体は。

今回は讃岐うどんの美味しさについて記事にしてみました。
美味しいと言いましても好みや個人差があります。
讃岐うどんの場合はどういう経緯で皆美味しく感じるのかを記事にしてみました。
※下記書籍を参考に記事にさせて頂きました。
書籍名:おいしさの科学辞典
発行日:2003年6月10日発行
発行者:朝野邦造
発行所:株式会社 朝倉書店
「美味しい讃岐うどん」の正体は。
●民族や集団の食文化に依存する美味しさ
美味しさは文化にも依存します。
食文化は地域の人々の嗜好と必要性の集大成だそうです。
讃岐うどんは香川県の文化です。
幼いころから、食べ慣れた味と香りは美味しいと感じやすいとありました。
トップアスリートが海外遠征にカップ味噌汁を持ち歩くのも、幼いころから食べ慣れているからこそですね。
香川県は県内に約700店のうどん店があり、毎日お昼はうどんを食べている方も多いです。
香川県民には潜在意識の中に「やっぱり自分はうどん県の人間」で毎日、うどんを食べるのが当たり前という慣習が根付いているのかもしれません。

※製麺所の生業はうどん玉卸。茹で上がって時間が経過しても美味しくなければいけません。
●空腹時の美味しさと旨味
美味しいと感じるのは生理に基づくものです。
一番は空腹時や栄養の欠如時です。
人間の本能として口にいれても大丈夫かどうかの判断を味覚で行うそうです。
口に入れた段階で苦い、不味いの類は人体に悪影響を及ぼすと遺伝子レベルで組み込まれています。
その中でも「旨味」や「甘み」は人体にとっても大切な栄養素である場合が多いので、人間も美味しいと感じやすい仕組みが確立されているようですね。
ちなみに「旨味」の主成分は植物性のグルタミン酸や動物性のイノシン酸で人体に必要なタンパク質の代表的な味覚だそうです(諸説あり)。
昆布やイリコの旨味の主成分ですね。
旨味を感じるということは、人間がたんぱく質を摂取している状態ということです。

※伊吹島産のいりこは身が引き締まり、独特の旨味があります。讃岐うどんには「伊吹いりこ」です!
●甘みの美味しさについて
甘みは「糖」を示す味覚のシグナルだそうです。
特に食糧不足の時代だった戦中戦後は、ほとんどの人間はエネルギー不足です。
この時代は甘みが最も美味しい味だったのは間違いないようで、甘い味付けのキャラメル等は飛ぶような人気でした。
余談ですが、戦後、愛媛県松山市内の鍋焼きうどん専門店は貴重な「甘み」を前面に押し出した味付けで一躍ソウルフードに上り詰めたようです。
甘みが美味しいと感じるのは人体が糖分不足かもしれませんね。

※松山市内「鍋焼き専門店 アサヒ」さん。戦後すぐに甘い食べ物が不足しているので、近所の方に甘い「鍋焼きうどん」を振る舞われたのがはじまりです。
→【番外編】徒歩10秒でハシゴ出来る。松山市内の老舗「鍋焼きうどん」専門店をご紹介。
●美味しいうどんの正体とは
基本的な味は甘・塩・酸・苦・うま味の5種類です。
美味しいとは5種類の味覚の微妙なバランスと質だそうです。
出汁など味覚に分類されるものは微妙なバランスと各々素材の質が大切です。
取材時に店主さんもよく「出汁はバランス」と仰います。
しかし、讃岐うどんはうどんの食感やのど越し等、味や旨味以外の付加要素で語られることが多い不思議な食べ物です。
咀嚼(そしゃく)の噛む、つぶす、それに伴う粘り気は美味しさとは直接結びつかないようです。(※諸説あります)
美味しいうどん、好きなうどんの正体は自分の食生活や食べるスピード等、各々が積み重ねてきた食生活の集大成なのかも知れません。
それが、各々讃岐うどんの好みとして現れるのかもしれませんね。

※高松市内「清水屋」さんのかけうどん。このプルプルのうどんは出汁も含めて絶妙なバランスで成り立っています。
→高松市内の人気讃岐うどん店「清水屋」さんをご紹介。人気メニューやうどんのこだわりについてお聞きしました。

この記事を書いた人
アユム・スカシヒット(株)一誠社http://isseisha.co.jp/
- TOP
- 讃岐うどんに関するまとめ記事やネタ情報
- 「美味しい讃岐うどん」の正体は。