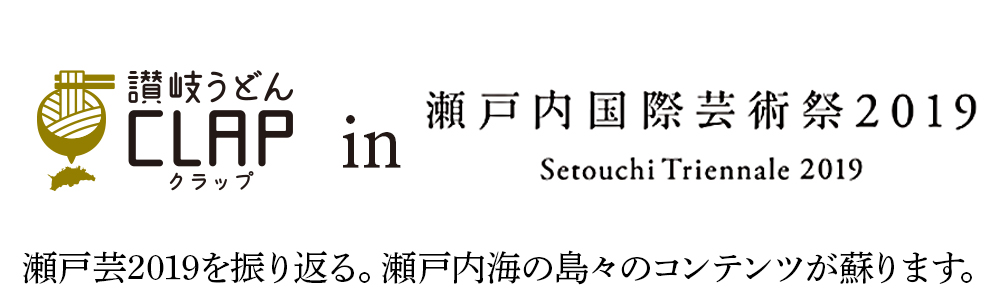「さぬきうどん研究会」多田会長インタビュー〜香川県産小麦 さぬきの夢誕生秘話〜
- 2024.12.11

うどん技術製造向上に伴う製麺業の発展と県内小麦の利用拡大を目的に開催された「さぬきの夢」うどん技能グランプリが開催されました。
グランプリ審査員長であり、さぬきうどん研究会会長でもある多田伸司さん。
長きにわたり、香川県産小麦「さぬきの夢」開発に携わられた多田会長に県産小麦やさぬきうどんについて貴重なお話を伺いました。
「さぬきうどん研究会」多田会長インタビュー〜香川県産小麦 さぬきの夢誕生秘話〜
ーー「さぬきの夢」うどん技能グランプリの審査員長として。
うどんの技能審査というのは、大変難しいですよね。
審査のやり方は最初に食べたうどんとそれ以降の比較になります。一つ目のうどんとそれ以降のうどんを比較して美味しいか、そうでないかという採点方法にならざるを得ませんから。
どうしても、最初のうどんの得点次第で後半に上振れしたり、下振れしたりしてしまいますね。
毎年、出品されるうどんはレベルが高くて、甲乙つけ難い年もありました…色々と迷い出したら、点数が決められません。
採点の際に大切にしていることは、ひと口食べた時の直感で決めています(笑)。
迷いだしたら、とても決められそうにありません。

※「『さぬきの夢』うどん技能グランプリの審査は本当に難しいです。うどんは見た目の出来栄えと食べた時の第一印象が大事だと思います」と多田会長。
ーーさぬきうどん研究会とは。
設立は40年ほど前、昭和59年です。
当時の香川大学農学部の真鍋先生が発起人となって、立ち上げられました。
目的はさぬきうどんの伝統を継承発展を図ること、文化的技術的発展を伴う云々…簡単に言いますと、うどんをキーワードに多方面から、可能な限り客観的な引いた目でうどんを考えるみたいなことですね。
さぬきうどんを面白おかしく取り上げるのではなく、可能な限り数値や専門的知見のような、裏付けがとれることを積極的に取って、積み上げて後世に残していこうというものです。
活動内容は各地のうどん食文化、麺食文化全般の専門家の方の講演会を開いたり、さぬきうどんの普及活動でイベント開催です。学校などでさぬきうどんの文化や伝統の体験教室を各地で行なっています。
県産小麦の「さぬきの夢」は小学校等への普及活動の成果もあり、小さなお子様の認知度は意外に高いのではないでしょうか。
先日、開催されましたさぬきの夢技能グランプリもそれらの普及活動のひとつになります。
実は私自身は香川県の県職員でしたがご縁があり、さぬきうどん研究会に属するようになりました。

※小学生等を対象に県内の様々なところでうどん打ち体験も開催されています。

※香川県の大切な食文化である讃岐うどん。多くの方々の地道な活動のおかげで讃岐うどん文化は支えられています。
ーー「初代さぬきの夢」の誕生。
私は昭和52年に香川県庁に入庁して、しばらくして、当時高松市仏生山にあった農業試験場で稲と麦の栽培担当になりました。
平成3年に香川県産小麦の品種開発を立ち上げようとなりました。
当時から、香川県にとって、さぬきうどんはシンボルと言える存在でしたが、県内のうどん屋さんで使われている小麦はASW(オーストラリア産小麦)が多く、香川県産小麦はほとんど使われていなかったんですよ。
「それではまずいだろう」
ということで、県産小麦が必要だということとなり、私が香川県産小麦の開発を任されたのがはじまりですね。
それが「さぬきの夢」となるわけです。
当時、県産小麦はあることはあったのですが、お世辞にも美味しいとはいえず、製麺性も悪いので酷評されていたように思います。
そこに改良を加えて完成したのが「さぬきの夢2000」です。いわゆる、「初代さぬきの夢」ですね。
これは、ひと言でいうと、
「人を選ぶ、打ち手を選ぶ小麦粉」
でしてね…扱い大変が難しいんですよね。
木下製粉の木下社長も仰られてましたが、テニスラケットで例えるとスイートスポットが極端に狭い。狭いけれど、スイートスポットに当たれば、素晴らしい打球になるといった感じです(笑)。
小麦特有の食味や香りは素晴らしいのですが、製麺性に難があり、選ばれたうどん職人しか上手に扱えなかったという印象です。製麺性でいえば、ASWが断然使いやすいですからね。

※「初代さぬきの夢でしっかり製麺出来る職人は腕が良い証でもあり、ある意味ステータスにもなっていました(笑)」と多田会長。

※「さぬきの夢は小麦の食味が感じられる」と木下社長。※2020年取材時

※さぬきの夢と他小麦をブレンドするうどん屋さんもあり、さぬきうどん業界は日々進化を遂げています。
ーー初代さぬきの夢の製麺性とASWの比較。
なぜ、「さぬきの夢2000」の扱いが難しいのか…それはたんぱく質におけるグルテンの質が弱いんです。
うどん生地にする際にグルテンの質が弱いため、製麺性や保存性がどうしても弱くなります。
2009になって、こちらはかなり改良出来ましたが、どうしてもASWと比較すると見劣りするんですよ。
ASWはオーストラリアなのですが、香川県全体の小麦作付面積が約2,500ヘクタールです。それは、オーストラリアの小麦農家一軒分の作付面積ですから…栽培規模でいったら、オーストラリアと比較にならないですよね。
研究費でみても、ASWは日本全体の麺食市場をマーケットにしてますから、比較しても規格外です。

※「小麦の新品種開発は通常交配から15年以上かかります、さぬきの夢は8年で出来ました。そのスピード感は素晴らしかったと思います」
ーー難しい小麦の新品種開発。
小麦開発というのはとにかくリスクが大きいんですよ。
通常、新品種の開発というのは交配から、最低でも10年はかかります。
交配段階から、でんぷんやグルテンの特性を見越して、交配組み合わせを進めるのですが、予定通りの品質が出来るとは限らないんですよ。
開発コストが非常に高く、民間企業だけで開発するのは技術的にも資金的にも大変難しいんです。
それを思うと、初代さぬきの夢がたった8年で出来たことは運が良かったんでしょうね。
もちろん、8年で完成までこぎつけた運というのは、研究者をはじめ、関与される皆様の日々の努力の賜物です。

※先般発表された開発中の「さぬきの夢2023」。多くの方々の技術と努力、勇気によって、県産小麦は今も開発されています。
ーーうどん職人と小麦の関係。
香川県のうどん屋さんに県産小麦を使ってもらう、ということは現在の小麦粉から変更するということです。
小麦粉を変えるということが、うどん職人さんにとって、どれほど重要なことかとういうことを理解しなければなりません。
さぬきの夢も今回の「さぬきの夢2023」で味はもちろん、製麺性もASW並みに扱いやすくなると考えられます。うどん屋さんにとって、使い慣れたASWから、小麦粉を変えることは大きなリスクが生じます。
まず、小麦粉を変えると味が変わりますので、売上に直接影響します。
次にオペレーション、作業工程や調理手順も変えないと行けません。
うどん屋さんからみても、小麦を変えるということはそれくらい大変な選択なんですよね。
私は「さぬきの夢2023」には、開発に関わっていませんが…それでも、どんどん進化していく「さぬきの夢」が今後もどのように受け入れらるのか楽しみです。

※「香川県で人気な過水の高い麺は、でんぷんの中の成分アミロースが少ない品種に現れる特徴でモチモチした食感となりやすいんです」と多田会長。

※変化と進化を続ける、さぬきうどん業界。人気の源泉は美味しさであることは間違いありません。
ーー美味しい讃岐うどんの変遷。
私が開発に携わわっていた頃はグミみたいな食感のうどんは認められにくい傾向があり、好き嫌いがはっきり分かれる傾向があったように思います。
好きな人はとことん好きでしたけど…最近は香川県内のうどん屋さんでも、加水の高いうどんを提供するうどん屋さんが増えましたよね。
よく議論される「コシ」というのも、職人さんの打ち方で決まるんではないでしょうかね。うどんを踏んでぎりぎりまで、鍛えれば鍛えるほど美味しいと感じる「コシ」が生まれると言われていますね。
その辺りは、打ち手の好みや食べる人の嗜好で決められる評価のことですので…説明できませんからね。
「美味しいさぬきうどん」
とひと言に定義するのは無理ですよね、本当に多様化しています。
「さぬきの夢」も当初は県外の方に好評だったんですよ。
香川県内の方はうどんをあまり噛まないで食べますよね(笑)。
それと比較して、県外の方は割としっかりと咀嚼して食べます。「さぬきの夢」を使ったうどんは小麦本来の食味や香りを楽しめますので、県外の方は「うどんの味が美味しい」というアンケート結果が高かった記憶があります。
いずれにしても、さぬきうどんというのは、不確定なことが多いですよね。
私は数字や実験で裏付けされた現象はある程度の説明は出来ますけど…、例えば〇〇うどんの発祥は、さぬきうどんのコシの正体は云々…とか聞かれることもありますが、説明できない、本当のところは分からないことだらけです。
それがあるから、さぬきうどんは楽しいんでしょう。
大きな意味でいうと、さぬきうどんの多様性やおおらかさが、多くの方々の心をつかんで離さないのでしょうね。
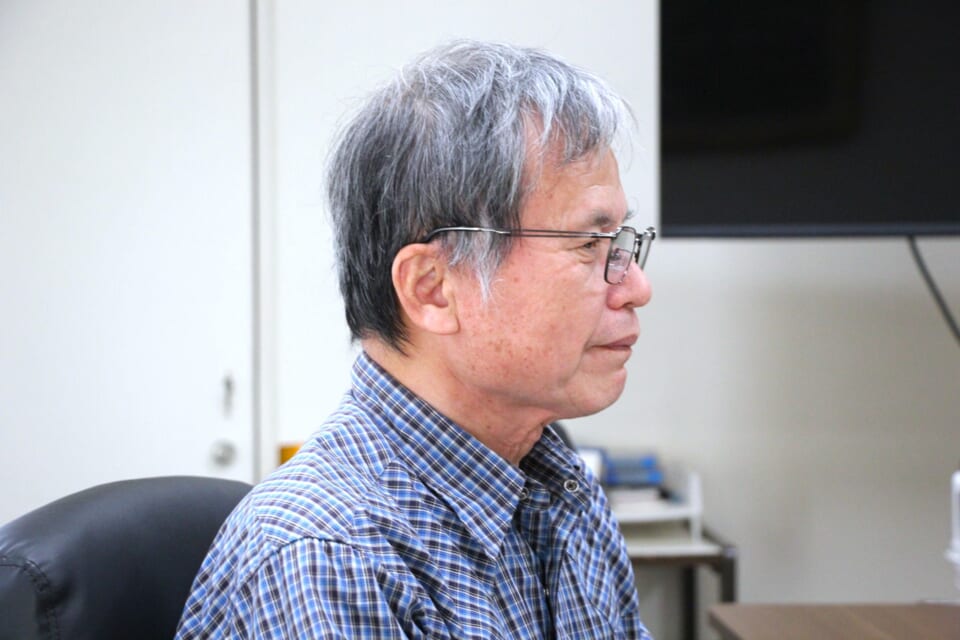
※長時間に渡り、気さくに取材に応じてくださった多田会長。お忙しいところ、ありがとうございました。

この記事を書いた人
アユム・スカシヒット(株)一誠社http://isseisha.co.jp/
- TOP
- 讃岐うどんに関するまとめ記事やネタ情報
- 「さぬきうどん研究会」多田会長インタビュー〜香川県産小麦 さぬきの夢誕生秘話〜